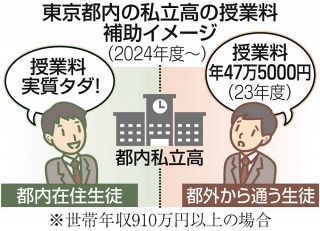若くして「介護離職」した女性が満足そうな理由とは? 写真はイメージです(写真:マハロ / PIXTA)病気、育児、介護、学業などによる離職・休職期間は、日本では「履歴書の空白」と呼ばれ、ネガティブに捉えられてきた。しかし、近年そうした期間を「キャリアブレイク」と呼び、肯定的に捉える文化が日本にも広まりつつある。この連載では、そんな「キャリアブレイク」の経験やその是非についてさまざまな人にインタビュー。その実際のところを描き出していく。
若くして「介護離職」した女性が満足そうな理由とは? 写真はイメージです(写真:マハロ / PIXTA)病気、育児、介護、学業などによる離職・休職期間は、日本では「履歴書の空白」と呼ばれ、ネガティブに捉えられてきた。しかし、近年そうした期間を「キャリアブレイク」と呼び、肯定的に捉える文化が日本にも広まりつつある。この連載では、そんな「キャリアブレイク」の経験やその是非についてさまざまな人にインタビュー。その実際のところを描き出していく。日本で介護離職をする人は、年間およそ10万人いるという(「令和4年就業構造基本調査」より)。再就職が難しかったり、就労意欲が低下したり、収入が減ったりすることから、介護離職は「キャリアの断絶」という文脈で語られることも多い。
しかし一方で、それをきっかけに、それまで縛られてきたキャリアを手放し、新たな人生への糸口をつかむ人もいる。今回は、そんな人のエピソードを紹介したい(なおプライバシー保護のため、情報の一部を改変しています)。
父親のがんをきっかけに退職
「どうやら、がんみたいなんだ」
父の突然の言葉だった。フランスで働いていた宮本みき(仮名、当時32歳)さんは、1週間の夏休みに帰国することを伝えるため、ひさしぶりに新潟の実家に電話をかけていた。
しかし、受話器越しに伝えられたのは、思いがけない事実。聞けば、ちょうど病院で告知を受けてきたところだという。
「父も病院にはほとんど行っていなかったようで、がんがわかったときには、かなり進行している状態でした」
宮本さんは、日本の音大を卒業後、輸出業を営む日本企業に26歳で就職。その後フランスに赴任し、6年目だった。当然、現地での仕事も、生活もある。しかし、決断は早かった。
「ショックというよりは、『やることをやらなきゃいけないな』という感じでしたね。手術がうまくいったとしても、入退院を繰り返すことになりそうだったんですが、兄と姉は実家の近くには住んでいない。私が一番動きやすい状況だったということもあり、『やるしかないな』と思いました」
宮本さんは、休職して帰国。実家で父親のケアを始めた。
父親は半年の治療後、自分で日常生活がほぼ支障なくできるほどに回復。宮本さんには、フランスに戻るという選択肢もあったが、日本に残ることを決断する。その背景には、それまでの生活への違和感があった。
宮本さんは、3歳からクラシック音楽を学び始めた。専門はバイオリン。大学も音大に入り、演奏を続けた。経歴だけ聞くと、幼少期からやりたいことを見つけ、順風満帆に歩んできたようにも聞こえる。しかし、宮本さんは人知れず葛藤を抱えていたという。
「音楽をやれる環境が与えられたのは、恵まれていたと思うし、感謝もしているんですけど……ずっと苦しかったんですよね。今思えば、自分で選んだ道というよりは、親が敷いたレールの上をずっと歩んでいたのだと思います」
音大を卒業後、音楽の道を離れて渡欧した背景には、「敷かれたレール」から逃れたいという思いと、20年以上音楽の世界に身を浸していたことによるコンプレックスもあった。
「『自分は世間知らずだ』と思っていました。世の中の常識がわかっていない気がして、自信がなかったんです。だから、若いうちに一度、大変な環境に身を置いてみたいという気持ちがあり、フランスで働くことにしました」
しかし、待っていたのは、家と職場の往復ばかりの日々。仕事は忙しいうえに、やりたくて選んだというよりはレールから逃れたくてした選択なので、心も喜んでいない。フランスでの生活は、宮本さんにとってつらいものだった。
疲弊した日々を送る中、突然知らされたのが、父の病の知らせだった。「今では、父に助けられたっていう気もするんです」と、宮本さんは振り返る。
「誰も、『そんな環境にいていいのか』とは言わないんですよ。でも、このままじゃいけないことは、自分が1番知っていて。だから父が病気になったときに、『一度リセットしなさい』って言われてるような気がしたんです」
「今こそやるときじゃないか」と、音楽の仕事を始めた
家と職場の往復ばかりの日々に戻るイメージが湧かなかった宮本さんは、日本に残ることを決意。会社に退職の連絡をし、実家がある町の隣町に家を借りた。
無職になった宮本さんが、「これから日本で、どう生活していこう」と悩んでいた矢先、大学時代の先生から思わぬ連絡があった。「演奏の仕事の求人が、あなたの地元で出ているよ」。
聞けば、主に学校でバイオリンを演奏する仕事だという。世の中にある演奏の仕事は限られており、ましてやそれが地方で得られるなんて、めったにない機会だ。宮本さんは、「音楽を仕事にするタイミングがきたということなのかな」と思った。
「演奏からは何年も離れていましたけど、『今こそやるときじゃないか。もう一度音楽にちゃんと取り組まないと、あとで後悔するぞ』っていう、自分の声が聞こえてきました」
34歳で音楽に関わる仕事を始めた宮本さんは、紆余曲折がありながらもそれから16年後まで、この仕事を続けることになる。
はじめの3年は社員として。しかし、もともと聴覚過敏で人がたくさんいる場所が苦手だった宮本さんは、毎朝大勢がいる場に行かなければならない環境にストレスを抱え、3年目に休職。うつ病と診断されたこともあってすこし休んだのち、パートとして仕事に復帰した。
その後13年ほど、演奏の仕事や、単発の講師などの仕事を続けてきた宮本さんに、ふたたび転機が訪れる。父親のがんが再発したのだ。
それまで実家では、父親が「多系統萎縮症」を発症した母親の介護をしていた。「多系統萎縮症」は、筋肉のふるえやこわばり、運動障害などの機能不全が起こる進行性の病気で、母親は日常生活のなかでケアが必要になっていた。
しかし、ちょうどコロナ禍で、もし施設に入れてしまうと感染リスクの懸念から家族でも会うことが難しくなってしまう。それに、両親ともに人生の最期までなるべく家で過ごしたいという希望があった。そこで、基本的には自宅で父親が介護し、週末には宮本さんが訪れてサポートする、という生活が続いていた。
「いずれ、母の看取りをすることになりそうだな」。そう思っていた矢先、父親のがんが再発。母親の介護をどうするか、という問題が持ち上がった。
兄と姉は実家から離れて暮らし、仕事や家庭がある。宮本さんは独身で、きょうだいのなかでも一番実家の近くに住んでいることから、宮本さんが実家に引っ越して母親の介護や父親のケアを引き受けようと考えた。
しかし、16年間続けてきた仕事も手放したくない。「演奏の仕事のときは、実家から通うよ」と父親に伝えた。すんなり受け入れてもらえると期待していたが、返ってきたのは「仕事と介護との両立は、できないと思う」という言葉だった。
「『突然、明日は仕事でいないから、ということがあっては困る』と。父も、母の介護でかなり身を削ったからこそ、その大変さがわかっていたんだと思うんです」
だが、仕事を手放すのは不安だった。宮本さんは、「この仕事は一生続けたい」と反論。母親も、「私のために仕事を辞めてほしくない」と援護する。
しかし父親は、受け入れられない様子だった。そうするうちにも、父親の症状は進行し、自らの死に向けた準備を進めていた。「自分はそんなに長くないと思う。最後は家で逝きたいから、よろしく頼む」。そう伝えられた宮本さんに、選択の余地はなかった。
「父が家で逝けるように、看取りの要員として抜擢された感じですね。でも、いやだったわけではなく、私も『家での看取りっていいな』と感じたので、在宅での介護をやらせてほしい、と思いました」
介護離職が、呪縛から解放されるきっかけになった
結果的に宮本さんは仕事を辞め、離れて暮らす兄や姉とも協力しあいながら、実家で母親の介護と父親のケアをすることに。収入がなくなったため、一家の生活費は両親の貯蓄や年金を、母親の介護費用は母親自身の貯蓄をあてながら暮らすことになった。
そして2023年、自宅で父親を看取ることになる。
介護がきっかけで大事にしていた仕事を手放さなくてはならなくなったことに、後悔はないのだろうか。そう尋ねると、「まだ自分でも整理できてないんですが……」と前置きしつつ、「不安や焦りは、たしかにありました」と打ち明けてくれた。
「『働いていない』という状況って、世間的にみてどうなんだろう……と考えてしまって、居心地は良いものではありませんでした」
しかし、「今では、後悔よりもむしろ、仕事を手放してよかったって思っているんです」と、宮本さんは続ける。
「これは絶対言っちゃいけないと思ってたけど……私、クラシックって興味なかったんです。『自分が1番自分らしくいられるのは、この世界ではない』って、昔からどこかで気づいていました。今思えば、『この仕事を大事にしたい』っていう気持ちは、呪縛だったんですよね」
宮本さんは、違和感に気づきながら、離れられずにいたのだ。演奏の仕事は、誰もが望んで手に入れられるものではない。しかも、その仕事がアイデンティティになっていて、「この仕事をやっていなければ、自分らしくなくなってしまう」と思っていた。だから16年間、違和感があっても見て見ないふりをして、一生懸命その環境を守ってきたのだった。
しかしいつしか、自ら選び取ったはずの仕事が、自らを縛るものになっていた。苦しいけど、手放せない……。そんなとき、父の看取りと母の介護が、強制的に手放すきっかけを与えてくれた。
「これは、私がそう思い込もうとしているかもしれないんですが……またお父さんが辞めさせてくれたんだなって、今は思っているんです。そうまでしないと、自分では仕事を手放せなかったので。仕事よりも大切なことがあるっていうことを、気づかせてくれた気がします」
「なにもしてなくても自分は価値がある」と気づいた
現在宮本さんは、地元で一人で暮らしている。2023年の年末まで母親の在宅介護をしていたが、病状が進行したことと、精神的にも肉体的にも宮本さんの負担が大きくなったこともあり、2024年のはじめから母親は施設へのお試し入居を始めたのだそうだ。
久々にできた、ひとりの時間。「いま、ちょっと呆然としていて」と、宮本さんは現状を教えてくれた。
「今まで毎日やっていた介護がなくなって、燃え尽き症候群というか、ポツンと、無人島にいるような感じで。自分がどうやって生きていこうかを、考える時間になっています」
どうやって生きていこうかを考える中で、不安も湧いてくる。
「不安の種は、やっぱり仕事ですね。これから私に何ができるんだろうかとか、本当にいろいろと考えます」
しかし、今感じているのは不安だけではない。「実は、希望も感じているんです」と宮本さん。その希望とは、介護をする生活の中で父親や母親が気づかせてくれたことだ。
「以前は、『仕事をしているから、自分は価値があるんだ』って思ってました。だけど、介護をするなかで、人はたとえ動けなくなっても価値もあるし、権利もあるんだなと。だったら私も、別に何にもしなくても存在してていいんじゃないか、って思ったんです。これまでは『なにかをしなきゃ』って思って、仕事や介護に必死に取り組んできましたけど、今やっと『なにもしてなくてもいいんだな』っていう感覚を味わっている気がします」
ひとりになった今は、しっかり寝ること、食べることなど、「どうしたら、自分が元気に生活できるのか」を試しているという。それは、これまでの50年間の人生で、宮本さんが試すことができなかったことだ。
そして、次の仕事のことも考え始めているらしい。
「自分の貯蓄が底をつく前までに、再び働き始める予定です。いったんキャリアはストップしましたが、介護離職の経験が違う人生につながると信じて、新しい働き方にチャレンジしたいと考えています」
キャリアブレイクは、仕事から離れることで自分を見つめ直し、あらたな考え方を見いだす機会になることがある。仕事を賃労働に限らず、育児や介護といったケア労働まで含めてとらえれば、介護という役割から離れた宮本さんは、広い意味でのキャリアブレイクのさなかにいるのだろう。
「介護離職=キャリアの断絶」なのか?
宮本さんのエピソードにふれて、「介護離職があらたな人生への糸口になったというのは、貯蓄があったり介護が長期化しなかったりと、たまたま運が良かっただけじゃないか」と思う方もいるかもしれない。
実際に、介護うつや介護殺人がときおりニュースになるなど、介護に伴う経験は一人ひとり異なるものであり、精神的、肉体的、経済的に大きな負担を抱えてしまっている人もいる。そして、介護のようなケア労働が女性に押し付けられてきたという根深い歴史も見過ごせない。
しかし、「介護離職=キャリアの断絶」と決めつけてしまうことのリスクもある。介護離職のつらさのひとつは、社会的な孤立だといわれる。周りの誰かが「介護離職=キャリアの断絶」と決めつけることは、本当は100人100通りであるはずの経験をひとつのストーリーに押し込め、当事者を孤立させることにつながるのではないだろうか。
無職・休職者がかならずしも怠惰だとはいえないように、介護離職者を「キャリアが断絶した人」としてだけ捉えると、見落としてしまうことがある。一人の個人としても、社会としても、介護離職者一人ひとりの声に耳を傾けていたい。
 山中散歩さんによるキャリアブレイク連載、過去記事はこちらから病気、育児、介護、学業など、さまざまな理由で、働くことができない時期があった方を募集しています。取材にご協力いただけます方、ご応募はこちらよりお願いいたします。
山中散歩さんによるキャリアブレイク連載、過去記事はこちらから病気、育児、介護、学業など、さまざまな理由で、働くことができない時期があった方を募集しています。取材にご協力いただけます方、ご応募はこちらよりお願いいたします。 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。