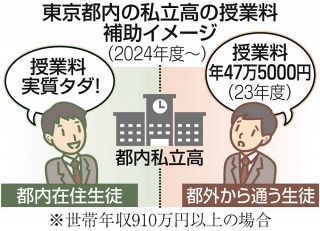辞職届を出す心境を問われ、細川ガラシャの辞世の句を引用した川勝知事(左)記者会見する川勝平太知事(写真:共同)(右)細川ガラシャ像(写真:まりーな / PIXTA)静岡県の川勝平太知事が、辞職届を提出する心境を聞かれた際に、細川ガラシャの辞世の句を詠んだことが話題となっている。果たして、辞世の句にはどんな感情が込められていたのか。真山知幸氏が上梓した歴史物語『泣ける日本史 教科書に残らないけど心に残る歴史』を一部抜粋・再構成し、細川ガラシャの物語をお送りする。
辞職届を出す心境を問われ、細川ガラシャの辞世の句を引用した川勝知事(左)記者会見する川勝平太知事(写真:共同)(右)細川ガラシャ像(写真:まりーな / PIXTA)静岡県の川勝平太知事が、辞職届を提出する心境を聞かれた際に、細川ガラシャの辞世の句を詠んだことが話題となっている。果たして、辞世の句にはどんな感情が込められていたのか。真山知幸氏が上梓した歴史物語『泣ける日本史 教科書に残らないけど心に残る歴史』を一部抜粋・再構成し、細川ガラシャの物語をお送りする。「京都馬揃え」を見事に仕切った父の明智光秀
天正9年(1581年)2月28日、「京都馬揃え」が開催された。織田信長による軍事パレードである。
馬揃えのルートは、本能寺から室町通りを北上し、一条通りを曲がって入った内裏の馬場へと到着する。内裏の東側には、天皇や公家が観覧する仮御殿も建てられた。
華麗な軍装をまとった騎馬武者たちが練り歩く。信長とその一門、家臣の武将たちに、お供の兵も加えて、6万人以上が行進に参加した。
「なんて豪華な……」
そう思わず漏らしたのは、観覧席で観ていた玉(のちの細川ガラシャ)である。パレードの見物には、武将の家族や町の人々も訪れた。玉は姉妹とともに、父が用意してくれた席で、きらびやかな行進に目を奪われていた。
1番手の丹羽長秀、2番手の蜂屋頼隆に次いで、早くも3番手として現れたのが、明智光秀である。
「父上が来たわ!」
玉がそう声を挙げると、ほかの3姉妹、倫、菊、鈴も目を輝かせた。特に倫は夫の秀光、菊は夫の光忠が、光秀の隊にいたため、少し照れたような笑みを浮かべた。
光秀の表情には、この大イベントの準備をやり切ったという自信がみなぎっているかのようだった。
「父上、ここまでの努力が報われましたね」
玉は感慨深い思いに駆られながら、我が夫が現れるのを心待ちにした。玉の夫は細川忠興。その父は細川藤孝で、光秀と同じく信長がその能力を高く評価する家臣だった。
信長は、光秀と藤孝という優秀な家臣同士を結婚させることで、織田軍団をさらに強化しようと考えていたのだろう。
5番目にこのイベントの主役である信長が嫡男の信忠とともに現れると、その壮麗さに観覧席にどよめきが走った。そして、信長の隊にいたのが、鈴の夫である信澄と、玉の夫、忠興である。
「忠興様……!」
忠興の堂々たる風格を目の当たりにして、玉の胸に誇らしい気持ちが沸き上がってきた。
つくづく人生はわからないものだ、と、玉はパレードを観ながら、しみじみと考えていた。
夫の細川忠興もまた出世頭だった
玉が最愛の母を亡くしたのは、忠興との縁組みが決まったすぐあとのことだった。いつも仲の良い両親を観ていた玉。憧れの夫婦とは、2人のようなことだといつも密かに思っていた。
それだけに母を失ったときのショックは計り知れないものだったが、玉を心配させたのは、元気のない父の姿だ。父の寂しさを思えば、いつまでも下を向いてはいられない。
そう自分を奮い立たせていると、不思議なことに人生は好転し始めた。玉はこのパレードの2年前には、忠興との間に男の子を産んでいる。名は忠隆という。
 勝竜寺城公園 細川忠興・玉(ガラシャ)像(写真: soulman / PIXTA)
勝竜寺城公園 細川忠興・玉(ガラシャ)像(写真: soulman / PIXTA)ちょうどその頃、丹波・丹後を平定した褒美として、信長から光秀に丹波一国を、藤孝と忠興に丹後一国を与えられたばかりだった。玉からすれば、父と夫がともに出世を果たしたことになる。
それだけに玉の出産は、12万石の大名となった細川家に、さらに大きな喜びをもたらすことになった。このパレードもまるで、自分の幸福を祝福してくれているかのように思えてくるほどだ。玉は、まさに幸福のまっただなかにいたのである。
「父上もすっかり元気になって、これからきっとまた新しい人生が始まるはずだわ」
しかし、その翌年に、すべての状況は一変することになる。
天正10年6月2日(1582年6月21日)、明智光秀が突如、主君を裏切って、本能寺にいる織田信長を討った。「本能寺の変」である。
「まさか、父上が信長様を……!」
玉は細川家の居城である宮津城で、父が謀反を起こしたという知らせを聞いたが、しばらくは受け入れられずにいた。
一体、何が起きているのか。到底、わかるはずもないが、安住の地が足元から崩れ去る不安はすぐに襲ってきた。玉は「裏切り者の娘」になったのだ。
行く末が不安な中、夫からの衝撃の一言
今、頼れるのは、ただ一人、夫の忠興だけ。行く末の不安をかき消すかのように、まだ2歳の忠隆をぎゅっと抱き締めて、つぶやいた。
「大丈夫、忠興様はきっと私を見捨てはしないはず……」
細川家と明智家はこれまでともに手を取り、戦乱の世をわたってきた。どんな事態になろうとも、その結びつきは揺るぎないと玉は信じて疑わなかったのである。
ところが、目の前に現れた忠興が放った言葉は、玉のそんな希望を無残に打ち砕くものだった。
「そなたには今すぐ、味土野(みどの)の別宅に行ってもらうことになった。時間がない。準備せよ」
「……私を離縁するということですか」
玉がすがるような眼で訴えると、忠興は目を背けて、無言でその場を立ち去った。それがすべての答えだった。
「これが現実に起きていることとは……」
まるで罪人のように粗末な籠に乗せられた玉。待女2人を連れて、人気のほとんどない山深い味土野へと幽閉されることとなったのである。
「子供たちと会いたい」
毎夜、月を見上げる玉。ある日、さらにどん底に叩き落す知らせが届いた。
「坂本城が落城……姉も弟たちもみんな炎のなかで自害……」
すでに父は討たれている。玉は、まさにすべてを失ったことになる。ただ一人行方知らずの妹の鈴をのぞけば、みないなくなってしまった。
「鈴だけは、どうか、鈴だけは……」
よほど自分も死んでしまおうかと何度も思ったが、玉は思いとどまった。2人目の子を宿していたからだ。私が細川家を守る。夫から離縁されてもなお、玉はそんな意思を固めていた。忠興が現れないのも、きっと何かの理由があるはず――。
そうして幽閉生活も2年が経ったころ、玉は宮津へと帰還が許される。ついに忠興が現れた。
夫・忠興の異常な愛情
忠興は玉に会うと、しっかりと抱きしめた。忠興は玉と復縁する許しを得るため、2年の間必死に秀吉に仕えていたのだ。一度、離縁したのも、明智家とのつながりがもはやないことを、秀吉に示すためであった。
「玉、会いたかった。離縁はそなたを守るためだった。ようやく太閤秀吉殿がお許しになられたのだ……」
秀吉……父を討った秀吉に私の命運は握られていたのか……そんな悔しさがなかったかといえば嘘になるが、安堵がそれに勝った。なにしろ、2年間、山にこもって、ひたすら将来を悲観する時間を過ごしたのだ。
忠興様を信じてよかった……また、ここから、夫と子供たちと人生を始めよう。玉は忠興の胸で涙にくれながら、何とか前を向こうとしていた。
しかし、夫の忠興の様子がおかしいことに気づくのに、そう時間はかからなかった。いつも見張られているような気配を感じながら、日々を過ごしているうちに、玉は忠興から外出を禁じられてしまう。
「一体、なぜなのですか!」
玉は抵抗するが、忠興は「一歩も出てはならぬ」と繰り返すのみ。そして、玉を抱きしめて、耳元でこうささやいたのである。
「もうどこにも行かせない。ずっと私のそばにいればよい」
嬉しい言葉のはずなのに、咄嗟に玉は忠興を突き飛ばしてしまった。
「ごめんなさい……」
忠興は薄ら笑いを浮かべながら、庭のほうへ目をやった。庭師がこちらに背を向けて木々の葉を切り、整えている。
「家中でも安全とは限らないか……」
そういうと、忠興はつかつかと庭へ降りて、庭師が振り返るや否や、刀で斬り付けて殺してしまった。
「人の妻に手を出そうとするからだ」
いうまでもなく、まったくの事実無根だが、忠興は不安でならなかった。
玉と再び暮らせる日を夢見て極限状態のなか戦っていた忠興は、ようやく取り戻した妻に異常な執着を見せるようになっていたのである。
「まるで鬼……」
嫉妬に狂った忠興により、場所は違えど、またもや幽閉生活を送らされることになった玉。もはや精神的な疲労も限界に来ていた。
「どうして私はこんな目ばかりに遭うのだろう」
そうため息をつくと、長男の忠隆が不思議そうにこっちを見ている。幽閉中に生まれた興秋も、もうずいぶんと大きくなった。
私はこの子たちのために細川家を守る。もっと強く、もっとしなやかにならないと。
石田三成軍に囲まれて壮絶な最期を
玉は忠興が戦に出かけると、こっそりと侍女を従えて出かけるようになった。行き先は教会である。
「主よ……」
玉がキリスト教に傾倒したのは、侍女のイトがきっかけだった。忠興と結婚して以来、イトは玉に仕えてくれている。いつもイトが祈り捧げているのを見て、玉も救い主に近づきたいという思いが日増しに強くなっていく。
ある日、ついにイトを通じて洗礼を受けた玉。これから人生をともにする、新たな名を与えられた。
「ガラシャ……」
ガラシャとは、ラテン語では「神の恵み」という意味を持つ。神に誓って、私は自分の役割をまっとうしてみせる――。
ガラシャが閉ざされた生活のなかで、そんな決意を固めているうちに、時代はまためぐる。慶長3(1598)年8月18日、秀吉が病死。豊臣家を支える重臣として台頭したのは、石田三成と徳川家康である。
忠興は家康側につき、長男の忠隆と次男の興秋を連れて出陣した。その隙を三成は見逃さなかった。ガラシャを人質としてとらえることで、細川家を西軍に引き入れようとしたのである。
「奥方様! 三成の軍勢が押し寄せてきて、屋敷が包囲されています!」
侍女たちが慌てふためくなか、玉は落ち着き払って言った。
「わかりました。マリア、みなを連れて、屋敷を出なさい。三成とて人質を粗末に扱いはしないでしょう」
マリアとは、イトの洗礼名である。イトには随分と助けられたと、玉は改めて感謝のまなざしを送った。
「しかし、奥方様を置いてはいけません」
玉はかぶりを振ると、みなを真っ直ぐみてほほ笑んだ。
「私は細川忠興の妻です。最期は私に見届けさせてください」
戦のことはよくわからない。だけれども、細川家を守るためには、こんな汚い手に出る敵の手に落ちるわけにはいかない……玉はみなが避難するのを見届けると、残った小笠原少斎を呼び寄せて言った。
「あなたには、嫌な役回りをさせてしまうことになり、申し訳なく思っています」
少斎は言葉も出ず、ただ首を振るのみ。すでに屋敷中に火は放ってある。三成に自分の遺体を渡さないために、玉があらかじめ指示していたことだった。
細川ガラシャの辞世の句
 『泣ける日本史 教科書に残らないけど心に残る歴史』(文響社)。書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします
『泣ける日本史 教科書に残らないけど心に残る歴史』(文響社)。書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプしますそして、最期に重要な任務が少斎には課せられていた。
「では、よろしく頼みますね」
少斎はうなずくと、泣きながら、玉の胸を槍で一突きにした。
すべては細川家にこれ以上の迷惑をかけないため……。キリシタンは自殺を禁じられているので、玉は少斎に自分の処刑を頼んでいたのだ。
「散りぬへき 時しりてこそ世の中の 花も花なれ 人も人なれ」
花は散る時を知ってこその花なのであり、人間もそうあらねばならない、今こそ散る時である――。
歌の作者は、細川ガラシャ。胸を突かれて意識が遠のくなか、ガラシャはあの日のきらびやかなパレードを思い出していたのかもしれない。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。